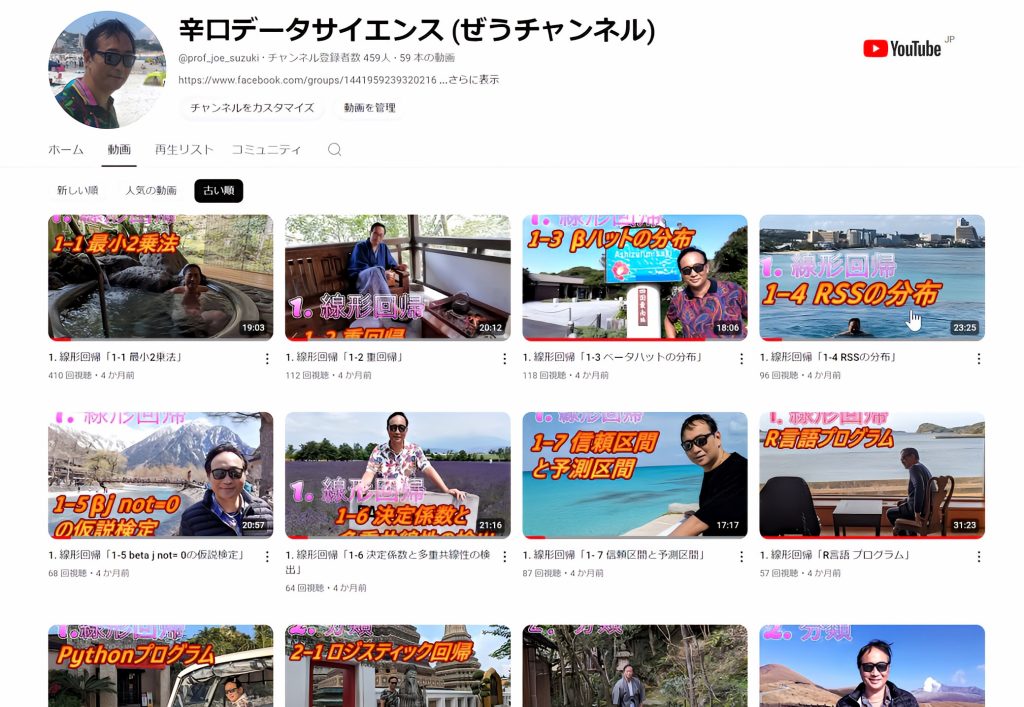$(\Omega,{\cal F},P)$を確率空間とします。$\mathbb R$に値をとるいわゆる確率変数は、$\Omega\ni \omega \mapsto X(\omega)\in {\mathbb R}$が可測であることが定義になります。同様に、Hilbert空間$H$について、$\Omega\ni \omega \mapsto F(\omega)\in H$が可測であるとき、$F$をランダム要素とよびます。ランダムな関数という言い方をしてもよいでしょう。ランダム要素は、$g\in H$と$r>0$について、$\{\omega\in \Omega\mid \|F(\omega)-g\|_H<r\}$が$\cal F$の要素ということができます。ここでは、「${\cal F}$がランダム要素であることと、任意の$f\in H$について$\langle F,f\rangle_H$が確率変数であることが同値」であることを示します。
以下では、$h\in H$と$a>0$を用いて$\{g\in H\mid \|g-h\|_H<a\}$とかける集合によって生成される$\sigma$集合体を$\sigma$、$h\in H$と$a\in {\mathbb R}$を用いて$\{g\in H\mid \langle g,h\rangle_H<a\}$とかける集合によって生成される$\sigma$集合体を$\sigma’$と書くものとします。このとき、$\sigma=\sigma’$が成立します(T. Hsing and R. Eubank, 2015)。その証明は最後に行うとして、認めて議論をすすめます。
まず、各$f\in H$について、$\varphi: H\ni g\rightarrow \langle g,f\rangle_H\in {\mathbb R}$は連続($|g-g’|<\epsilon \Longrightarrow |\langle g,f\rangle-\langle g’,f\rangle|\leq |g-g’|\cdot|f|<|f|\epsilon$)なので、$\langle F,f\rangle$は可測になります。逆に各$f\in H$について$\langle F,f\rangle$が可測であれば、各$a\in {\mathbb R}$について
$$F^{-1}\{g\in H\mid \langle g, f\rangle <a\}=\{\omega\in\Omega \mid \langle F(\omega),f\rangle <a\}\in {\cal F}$$となり、$\sigma=\sigma’$から$F$は可測、すなわち$H$のランダム要素になります。
このことから$f: \Omega\times E\rightarrow {\mathbb R}$が可測であって各$\omega\in \Omega$で$f(\omega,\cdot)\in H$であれば、$\Omega\ni\omega \mapsto f(\omega,\cdot)$は$H$のランダム要素になります。実際、各$h\in H$で$\langle f(\omega,\cdot),h\rangle $が可測になるので、$f(\omega,\cdot)\in H$, $\omega\in \Omega$であれば、ランダム要素になります。
$\sigma=\sigma’$の証明:
各$f\in H$について、$\varphi: H\ni g\rightarrow \langle g,f\rangle_H\in {\mathbb R}$は連続なので、${\mathbb R}$の任意の開集合$B$の逆像$\varphi^{-1}(B)\subseteq H$も開集合となります。したがって、$\sigma’\subseteq \sigma$が成立します。次に、逆方向の包含関係を示します。$\{e_i\}$を$H$の正規直交基底として、
\begin{eqnarray*}
&&\{g\in H\mid \langle g, e_1\rangle^2+\langle g,e_2\rangle^2<\epsilon\}\\
&=&\cup_{q\in {\mathbb Q}}\left(\{g\in H\mid \langle g,e_1\rangle^2<q\}\cap \{g\in H\mid \langle g,e_2\rangle^2<\epsilon^2-q\}\right)\in \sigma’\\
&&\{g\in H\mid \sum_{j=1}{i-1}\langle g, e_j\rangle^2+\langle g,e_i\rangle^2<\epsilon\}\\
&=&\cup_{q\in {\mathbb Q}}\left(\{g\in H\mid \langle g,\sum_{j=1}^{i-1}e_j\rangle^2<q\}\cap \{g\in H\mid \langle g,e_i\rangle^2<\epsilon^2-q\}\right)\in \sigma’\end{eqnarray*}より、帰納法から以下が得られます。
$$\{g\in H\mid \|g|<\epsilon\}=\cup_{j=1}^\infty \left\{g\in H\mid \sum_{k=1}^j\langle g,e_k\rangle^2<\epsilon^2 \right\}\in \sigma’$$ したがって、任意の$\{g\in H\mid \|g-h\|<\epsilon\}\in \sigma$が以下のようにかけます。
$$\cup_{q\in {\mathbb Q}} \left(
\{g\in H\mid \|g\|^2<q\}\cup\{g\in H\mid 2\langle g,h\rangle>q-\epsilon^2+\|h\|^2
\}\right)$$ここで、$\{g\in H\mid \|g\|^2<q\}$はこれまでの議論から$\sigma’$の要素、第2項はもともと$\sigma’$ですから、全体として$\sigma’$の要素です。したがって、$\sigma\subseteq \sigma’$が成立します。